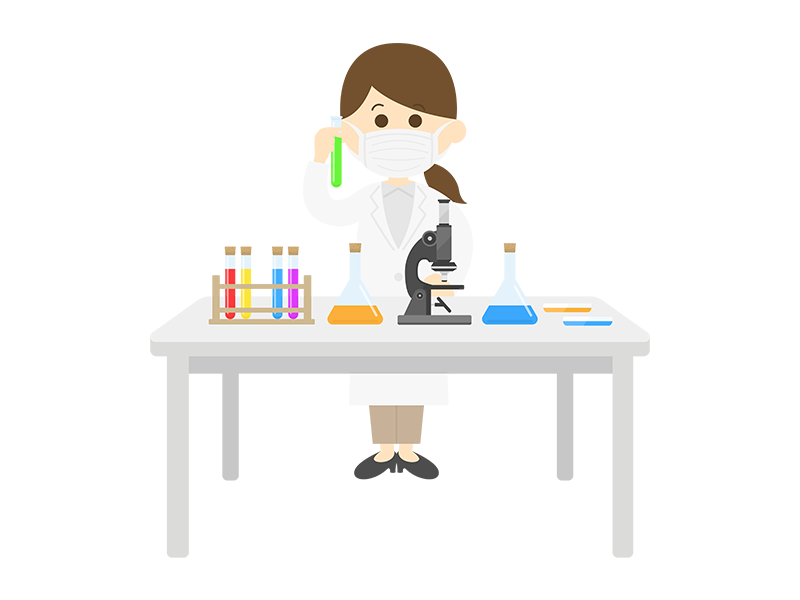粉骨する際に、確かに六価クロム(Cr⁶⁺)が発生する可能性はあります。
ただ、正確に言うと粉骨する遺骨にもともと六価クロムが含まれていて、粉骨作業中に六価クロムが増える、大気中に広がって誤って吸引してしまう恐れがある、ということです。
六価クロムとは
六価クロム(Cr⁶⁺、ろっかクロム)とは、クロム(Cr:原子番号24)が酸化された状態の一つで、「発がん性物質」です。非常に強い酸化力と毒性を持つ有害化合物です。
六価クロムは「発がん性物質」であり、注意が必要
六価クロム(Cr⁶⁺)は強い酸化力と発がん性をもつ有害重金属化合物です。
そのため、
・粉骨時に粉塵として吸い込む
・水に溶けて溶出する
といった経路で健康被害を生む可能性があります。吸引してしまった場合は呼吸器系に深刻な影響を及ぼすことがあります。喉の痛みや刺激感、倦怠感、肺炎や肺浮腫(重症の場合)肺がんや鼻腔・副鼻腔のがんのリスク増加など、注意が必要です。
工場の排水などに含まれていることがあり、酸性が強く川や海に流すと魚や人に悪い影響があります。(ただし、通常の火葬遺骨の六価クロム濃度はごく微量で、多くは安全域内にあります。)
なぜ六価クロムが遺骨・粉骨に発生するの?その仕組み
有害物質である六価クロムは、主に火葬中に発生することが多いです。そのメカニズムは、以下の通りです。
火葬で金属が変質する
六価クロムは「焼骨中に微量に発生する」ことがあります。
火葬の際、高温(約800~1000℃)でステンレスなどの金属(クロムを含む合金)が一緒に焼かれると、酸化反応により三価クロム(Cr³⁺)が六価クロム(Cr⁶⁺)に変化することがあります。
たとえば、
・入れ歯や金属冠(歯の詰め物)
・医療用金属(インプラント・ボルトなど)
・棺の金属装飾部
これらに含まれるクロムが、焼却中に酸化して六価クロムとなり、遺骨や炉内灰中に微量に混入することがあるのです。
粉骨時の摩擦・熱
粉骨機で骨を砕く際に摩擦熱が発生すると、六価クロムが微量ながら粉塵中に含まれることがあります。
特に、業務用の高出力粉骨機を使用する場合は、より高温になりやすく、発生リスクが高まるとされています。
粉骨の六価クロムはどれくらい危険なの?
六価クロムが粉骨後の骨粉に「微量」含まれる程度で、直ちに人体に重大な影響を及ぼすわけではないとされています。
ただし、粉骨作業を頻繁に行う業者や、作業時に適切な防護対策(マスク・換気など)をしていない場合は、吸引による健康リスクがあります。
六価クロムへの安全対策のポイント
「粉骨処理」と同時に六価クロム除去・中和が重要
粉骨作業を行う際に、遺骨に六価クロムが残留していると、粉塵の吸入や環境汚染の原因になります。
また、粉骨後のパウダー化した遺骨に六価クロムが残っていると屋内で保管した場合(自宅での手元供養や納骨施設)吸い込んでしまうリスクがあります。また散骨した場合、山や海に有害物質をまくこととなり自然の環境破壊にもつながります。
そのため、信頼できる粉骨業者では以下のような無毒化の対応を行います。
| 処理方法 | 内容 |
|---|---|
| 洗浄・乾燥工程 | 粉骨前に遺骨を水洗い・乾燥し、表面の金属酸化物(六価クロムなど)を除去。 |
| 中和液による処理 | 亜硫酸塩系の中和剤(例:亜硫酸ナトリウム Na₂SO₃)を使い、六価クロムを三価クロムに還元。 |
| 分析チェック | pHやクロム濃度を簡易測定して安全確認。 |
六価クロム(Cr⁶⁺)を中和・無害化するためには、まず「還元剤(還元中和剤)」を使って三価クロム(Cr³⁺)に還元する必要があります。
ここでいう「中和剤」とは、一般的には「六価クロムを還元して無害化する薬品」のことを指します。
六価クロムの中和(還元)剤一覧
| 名称 | 主な化学式 | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 亜硫酸ナトリウム(Na₂SO₃) | Na₂SO₃ | 最も一般的。扱いやすく反応が穏やか。pHを調整しやすい。 | 強酸性下で使用。反応後に硫酸塩が生成する。 |
| 亜硫酸水素ナトリウム(NaHSO₃) | NaHSO₃ | 還元力が強く、低pHでも反応しやすい。 | 酸性条件で二酸化硫黄(SO₂)が発生することがある。換気必要。 |
| 亜硫酸水素アンモニウム(NH₄HSO₃) | NH₄HSO₃ | 排水処理現場で使用例が多い。中和後の処理が容易。 | アンモニア臭が発生する。 |
| チオ硫酸ナトリウム(Na₂S₂O₃) | Na₂S₂O₃ | 安全性が高く、実験室や教育現場でよく使用。 | 還元力がやや弱い。高濃度の六価クロムには不向き。 |
| 鉄(Ⅱ)塩(硫酸鉄(Ⅱ)など) | FeSO₄ | 安価で大量処理向き。排水処理施設でよく使用。 | 生成する三価鉄が沈殿しやすく、処理後のスラッジ処理が必要。 |
その他の対策
密閉式の粉骨機を使用する
粉塵や熱が外に漏れにくく、作業者の安全性が高まります。
防塵マスクや手袋を着用する
粉塵の吸引や皮膚接触を避けるために重要です。
換気の良い場所で作業する
六価クロムの吸入リスクを下げるため、粉骨は屋内でも十分な換気が必要です。
粉骨は信頼できる業者に依頼するのがやっぱり安心
粉骨処理を自分で行わず、六価クロム対策が明示されている業者に依頼することで、安全性が高まります。六価クロムを中和させる薬品や機材を備えていて、対応してくれます。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 発生原因 | 火葬時に金属(クロム含有)から酸化生成される。 |
| 有害性 | 発がん性物質。吸入・水溶出に注意。 |
| 除去方法 | 洗浄+亜硫酸塩などによる還元中和。 |
| 安全対策 | 粉塵吸入防止・専門業者委託。 |
| 注意点 | 自宅粉骨時は安全装備・作業環境に留意。 |
もし粉骨を検討中であれば、六価クロム対策をしているかどうかを業者に確認することが安心です。
六価クロム除去のオプションの内容
当社「朔月(さくげつ)」でも、六価クロムを中和剤で無毒化する対策をしっかり行っています。
3000円~のオプションで、選択することが可能です。
六価クロム除去の流れ
【1】ご遺骨を受け取る・確認する
受け取った骨壺からお骨を確認します。特に「金属製の副葬品」や「骨壷の金属部品」などがあった場合、六価クロムが出やすいです。この段階で、金属片や不純物をできるだけ取り除きます。
【2】粉骨前の安全確認
骨の一部(灰)を少し取り、六価クロムのpH試験紙で確認します。紫色などに変わると「六価クロムが含まれている」と判断します。
【3】中和剤の準備
中和剤として使うのは、「亜硫酸ナトリウム」の液体です。業務用の高濃度中和剤をスプレーボトル(噴霧器)に入れて使います。
🔹この段階では「中和剤の希釈液(弱い酸性)」を作るイメージです。
【4】粉骨機に入れる前の処理
骨を粉砕機に入れる前、骨表面に中和剤を軽く噴霧します。スプレーのように「シュッ、シュッ」と霧状にかけるだけです。骨が軽く湿る程度で十分です。この噴霧によって、もし表面に六価クロムが付いていても中和されます。
【5】粉骨作業
骨を粉砕機(ミルなど)に入れて粉骨します。中和剤がかかっていることで、作業中に六価クロム粉じんが舞うリスクが大幅に下がります。粉骨後の粉にも、再度ごく少量の中和剤を霧状に噴霧する場合があります。
【6】洗浄
粉骨機の内部も、作業終了後に中和剤を含む水で拭き上げます。こうすることで、機械内部に六価クロムが残らないようにします。作業中は手袋・マスク・ゴーグルを着用し、換気を十分にします。
【7】乾燥
中和剤を使って湿らせた後は、必ず十分に乾燥させます。
中和剤を使うと、粉骨の表面が一時的に湿った状態になります。そのまま乾燥させないままだと、いろいろと問題が起きます(カビや臭いの原因、ダマになる、骨壷などに密閉すると、湿気がこもり内部で腐敗臭が出ることがある)。
乾燥器を使って40〜60℃程度で半日〜1日知時間をかけてじっくりと乾燥させます。触っても冷たさや湿り気を感じない状態。粉がサラサラとほぐれるようになるのが目安です。乾燥後に、再度pH試験紙で中和済みを確認します(中性〜弱アルカリなら安全)。